ユニットハウスとは?
ユニットハウスとは、建設現場の事務所や倉庫などで使われている箱型の建築物のことを指します。
「ユニットハウス」という言葉自体、さまざまなところで使われていますが、広く世の中に出まわっているものの多くは、この箱型の建築物のことを言います。
言葉の由来
そもそも『ユニット』という言葉は、1つの単位や集団を意味します。
建物を効率よく建てる方法として、1つの建物をいくつかのユニットに分け、建築現場とは別の場所で造り、建築現場ではそのユニットを組み合わせることで工期を短くするという良い方法が考えられました。
それらは『ユニット工法』と呼ばれ、1つのユニットである骨組みを組み合わせる建設の仕方は、今では一般的な工法となっています。
その1つのユニットそのものが建物として独立し、トラックに載せて運搬できるようにした建築物が『ユニットハウス』です。
規格化されたシンプル構造
ユニットハウスの基本フレームは、頑丈なスチール(鋼鉄)構造です。
1つのユニットでも、1つの建物として成り立つものもありますが、その規格化されたボックスフレーム(ユニット)を組み合わせることで、大小さまざまな建築空間を創り出します。
また、窓や壁、ドアなどはパネルを組み合わせることで自由に設定でき、思いのままの空間をスピーディに施工可能です。

ユニットハウスは、上の写真のようなスチール製フレームを1ユニットとして作られていきます。
1ユニットに、壁や窓などのパネルを付けることで「単棟」になります。

単棟のユニットハウスの場合、4tユニック車でそのまま運ぶことができます。
さらに、2つを横に組み合わせると2連棟に、3つで3連棟に・・・というふうに、かなり大きな建物や、重ねることで2階建てなどにすることも可能です。

スーパーハウスとは
元々は株式会社ナガワのユニットハウス商品名。
登録商標は株式会社ナガワが持つ。
ユニットハウスの別名として有名
1990年代に広くスーパーハウスがひろがったことから
ユニットハウスの別名として広く知れ渡っている。
ユニットハウスとプレハブの違い
よく、ユニットハウスとプレハブを同じものだと思っている方も多いようですが
2つは、根本的に違う点があります。
プレハブは、現場で組み立てる
ある程度部材を作ってから現場にもちこみ
現場で組み立てるのがプレハブです。
したがって
ユニットを作ってから現場で設置するユニットハウスに比べると
現場での施工時間が長くかかります。
ただし、部材をコンパクトに運べるため
ユニットハウスよりは輸送費がかからない場合が多いです。
1度出来てしまうと設置や移設が簡単なユニットハウス
プレハブと違い、ユニットハウスの場合は移設が容易です。
プレハブですと、いちいち解体作業が発生し、また組立も必要ですが
ユニットハウスは、ユニットをそのまま運ぶため
設置に時間がかからず、移設もプレハブに比べると圧倒的に簡単です。
また、ユニットハウスは、各メーカー共に間取りが決まっています。
材質的に耐久性が高いので長期使用でき
本体への不具合は各部分での修理対応が簡単です。
また、不要になった場合でも、転売等の方法が可能です。
他の場所への移設も簡単です。
しかし、基本的には4トンユニック車での搬入となる為
矮小道路・電線・立ち木・隣家等、設置の妨げになるような
障害物がある場所への設置は難しいです。
対してプレハブは、組み立て式である程度間取りが自由に選べます。
しかし、材質的に消耗度が大きく、長期使用は困難となります。
本体に不具合が生じた際の修理代も割高です。
また、不要になった場合には、廃材にしかなりません。
現地組み立てなので、4トンユニック車が入って行けない狭い場所や
電線等の障害物でクレーン作業が困難な場所への設置が可能です。
強度はユニットハウスが上
プレハブというと
かつて「プレハブ小屋」などと呼ばれたように
強度が弱いのが欠点だとされてきました。
その点、ユニットハウスは
強固なスチール製のフレームが基盤となったユニットなので
強度は、ユニットハウスが上の場合が多いです。
ただし
近年になって、プレハブ工法も進化しており
強度の高いものもあります。
建築確認について
建築確認とは
建築物を建築(新築、増築等)する時には、
建築基準法という建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。
この法律では建築物の
「工事を始める前」「工事途中で特に重要と指定した工程(一定規模以上の建築物の場合に限る)」
そして「工事が完了したとき」の3つのポイントで
建築基準関係規定(建築基準法・都市計画法・消防法等)に適合しているかどうかを、
都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関がチェックすることを定めています。
この中で「工事を始める前」にチェックを受けるために必要な手続きが「建築確認申請」です。
建築確認申請は、その計画内容(建築物の用途、構造、規模、敷地位置、形態等)について
図面・構造計算書等を用いてチェックを行い、住民の生命・健康等を守ること、
および良好な市街地環境を確保することを目的としています。
建築確認申請(法律での位置づけ)
建築主は、建築確認申請対象建築物を建築しようとする場合、
またはこれらの建築物の大規模な修繕もしくは大規模な模様替えをしようとする場合において、
当該工事着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、
確認の申請書を建築主事等に提出し、※確認済証の交付を受けなければならないと
建築基準法第6条で位置付けられています。
※確認済証について
建築確認申請が建築基準関係規定に適合していると認められたときには、
建築主事等から確認済証が交付されます。
これ以後、工事着手が可能となります。
つまり、確認済証が交付される前に基礎工事を始める(いわゆる事前着工)のは違法です。
建築確認申請の流れ
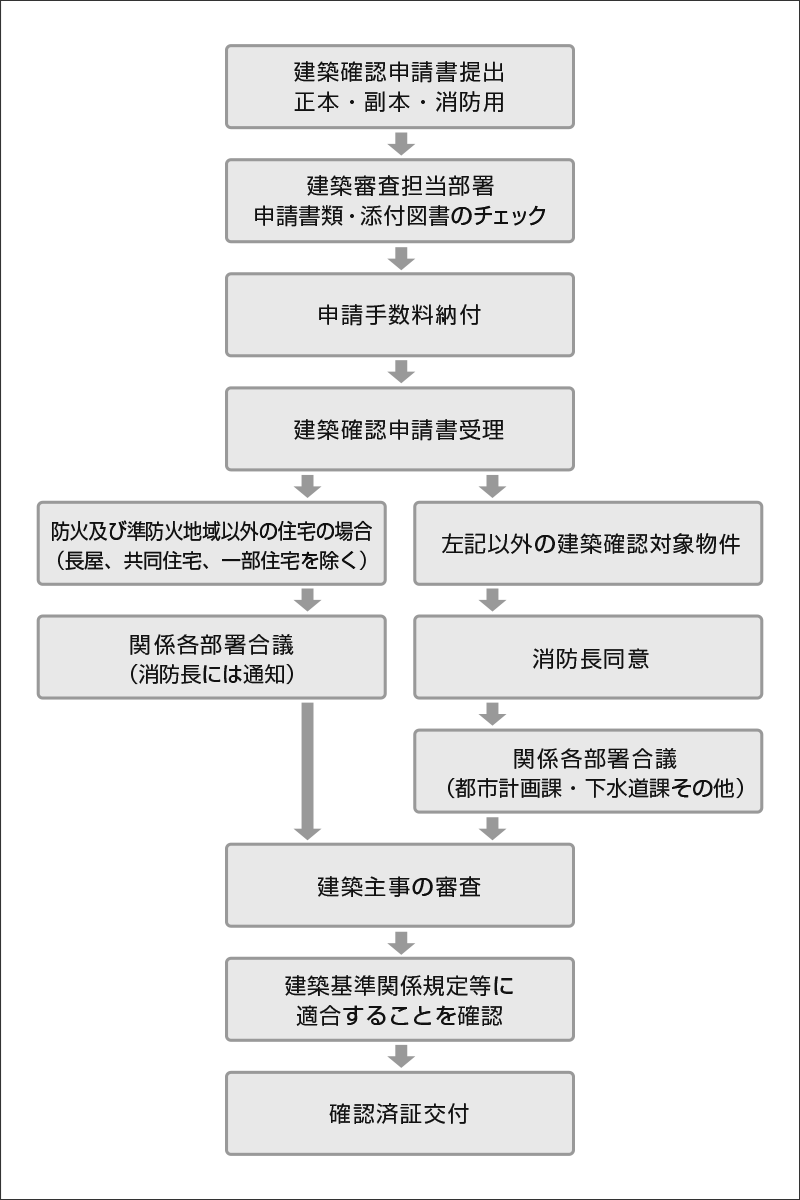
建築確認申請受付窓口にて確認申請書を受理した後、
その申請書は消防本部・都市計画課・下水道課等関係各課の合議を経て
建築主事の審査を受けることとなるため、
確認済証が交付されるまでには日数がかかります。
申請提出以前にその準備にも日数がかかりますので、日数短縮のためには、
事前にしっかりと調査をしておくことがとても重要となります。
建築確認申請対象のユニットハウス
▼建築確認申請が必要なケース▼
①更地にユニットハウスを設置する場合(新築)
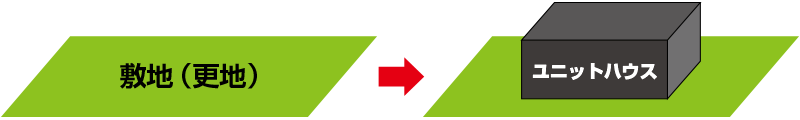
⇒床面積に関わらず建築確認申請が必要
②防火地域・準防火地域内でユニットハウスを設置する場合
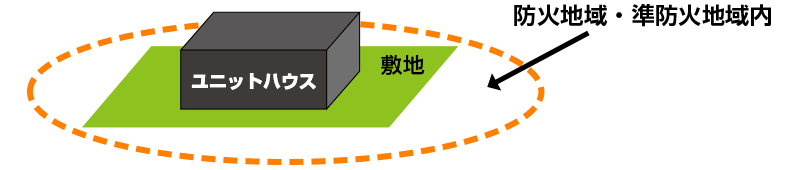
⇒床面積に関わらず建築確認申請が必要
③10㎡を超えるユニットハウスを既存建物がある敷地に設置する場合(増築)

⇒建築確認申請が必要
④10㎡を超えるユニットハウスを同一敷地内で移転する場合(移転)

⇒建築確認申請が必要
建築確認申請不要のユニットハウス・ミニ倉庫
▼建築確認申請が不要なケース▼

①10㎡以下のユニットハウス・倉庫を既存建物がある敷地に設置する場合(増築)

⇒建築確認申請不要
※ただし、既存建物は適法な建物であることが条件です。
②10㎡以下のユニットハウス・倉庫を同一敷地内で移転する場合(移転)

⇒建築確認申請不要